 公演チラシ
公演チラシ
東京に本拠を置く劇団「文化座」が第10回公演として張赫宙(チャン・ヒョクチュ、1905〜98/本名は張恩重、チャン・ウンヂュン)脚色の『春香伝』を新宿「帝都座」にて上演。演出は劇団代表の佐々木隆(1909〜67)。雑誌「日本演劇」1947年8月号に利倉幸一(1905〜85)による劇評「文化座の春香伝」が掲載された。文化座によるこの演劇実践は韓国の戯曲を日本の劇団が上演したことから、本稿では「戯曲交換」に分類する。
 公演チラシ
公演チラシ
1950年4月29日に国立劇団が創団されるにともない、1935年に建築された府民館を国立劇場として使用した。同年4月30日のこけら落としは柳致眞(ユ・チヂン、1905〜1974)の『元述郎(ウォンスルラン)』。
開館公演直後の1950年6月25日に韓国戦争(ユギオ)が勃発し、国立劇場はソウルを離れて大邱市に疎開した。ソウル還都後は明洞に所在する市公館(旧・明治座)をソウル市議会との共用で劇場として利用した。その後にソウル市議会が1961年に市民会館(旧府民館)へ移ったことから、明洞の市公館(旧・明治座)は1962年から国立劇場として使用されることになった。いま現在の中央国立劇場は1973年10月にソウル特別市中区獎忠洞に建設された劇場。
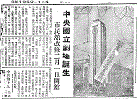 東亜日報「中央国立劇場誕生」
東亜日報「中央国立劇場誕生」
“獨鵑”崔象徳(“ドキョン”チェ・サンドク、1901〜70)を団長にパンソリの名唱として知られた林芳蔚(イム・バンウル、1904〜61)とコムンゴ奏者の“琴軒”申快童(“クモン”シン・ケドン、1910〜77)をはじめ朴貴姫(パク・キヒ/本名・呉桂花、1921〜1993)や“春鶯”林終禮(“チュネン”イム・ヂョンネ、1923〜75)など40人が来日し、『春香伝』を新宿松竹座(9/25〜30)をはじめ、名古屋・大阪・神戸・京都・福岡などで上演した。評論家のほんち・えいき(1925〜)は「テアトロ」(1985年12月号)のアンケート企画「戦後の来日公演ベストテン」にこの公演を選んだ。朝日新聞(1958/9/12)に「韓国と中国から芸術団/純粋の古典劇を公演」がある。
 朝日新聞「韓国と中国から芸術団/純粋の古典劇を公演」
朝日新聞「韓国と中国から芸術団/純粋の古典劇を公演」
創立10周年を迎えた劇団七曜会は記念公演として創作劇を連続上演することにし、その最初の作品として在日作家金達寿(キム・ダルス)原作・八木柊一郎脚色による『朴達の裁判』を3月11日から俳優座劇場で上演した。朝日新聞(1960/2/26)に関連記事「どぶろく屋も見学/朴達の裁判、劇化上演/七曜会が十周年記念に」がある。
 朝日新聞「どぶろく屋も見学/朴達の裁判、劇化上演」
朝日新聞「どぶろく屋も見学/朴達の裁判、劇化上演」
東亜日報は1961年12月21日付けの記事で同年12月29日に「韓國藝術文化團體綜聯合會(藝綜)」の創立大会が開催されると報道した。
記事リード「文化団体統合が着々と進行し、予定していたよりは少し遅く、来るクリスマスまでには各ジャンル別の統合が完了すると見える。十余年のあいだ四分八裂していた文化団体がこのように快速度でひと息に括られていることに、むしろ新しい不安を内包する憂慮も無くはないが、いずれにせよ形式的には単一の看板をの下に団結するわけだ。あるいはあまりにも性急に急き立てたとから、文化団体統合の内的な動機や本質的な意義からはずれていく憂慮も文化界の一部で表明される雰囲気。」

公報部が主導して各種文化芸術団体を統合した団体作りを行っていたが、演劇界も「韓國演劇協會」を発足させた。韓国演劇協会の発足を報じる朝鮮日報1961年12月28日付けの記事。

この記事の「国立劇場」は現在の「明洞芸術劇場」。解放前(戦前)は多目的ホールだった明洞所在の「明治座」を解放後に「市公館」として使用していたが、これを改造して「国立劇場」としたもの。開館記念公演はイ・ヨンチャン作/朴珍(パク・チン)演出の『若さの賛歌』。
ソウル特別市は南山のふもとに「ドラマセンター」が開館した。韓「ネイバー百科事典」に記載された「ドラマセンター」の紹介文は以下のとおり。
1960年、劇作家で演出家の「東朗」柳致眞(「トンナン」ユ・チヂン、1905〜1974)が米ロックフェラー財団からの財政支援によって着工し、1962年に竣工した約500席の半円形客席を持つ演劇専用の中規模劇場。設計は金重業(キム・ヂュンオプ)。財団法人韓国演劇研究所として出発し、設立者の柳致眞を所長として事務局長に申泰皎(シン・テミン)、劇場長に李海浪(イ・ヘラン)、アカデミー院長に呂石基(ヨ・ソッキ) などの陣容を取り揃えた。演劇中興と後進養成のための学習の場を兼ねて設計され、当時としては画期的な開放舞台(open stage)として構築された点が特徴であった。円形舞台はギリシア野外劇場の舞台に模したものであり、主舞台は近代劇の舞台形式である。その他に講義室を含めて図書館や作家室・衣裳室・楽屋など、演劇を学び上演するために必要な施設を取り揃えた。
1962年4月、こけら落としとして柳致眞演出の『ハムレット』を上演し、韓国演劇中興の騎手になると期待された。しかし観客不足と財政的基盤の脆弱性から財政難に陥り、翻訳劇中心の公演で韓国演劇の中興に寄与できなかったという批判の中で、けっきょく興行を主目的とする貸し劇場に変化した。
ドラマセンターは児童劇団「童演(トンヨン)」や専属劇団である「劇団ドラマセンター」を創立して多くの演劇人を養成し意慾的な演劇活動を開いた。「劇団ドラマセンター」は1974年に柳致眞が死んだ後に名称を、彼の号を取って「東朗レパートリー劇団」とし、1970年代に反写実主義演劇運動を展開して、韓国劇界に大きな変化を起こした劇団として注目された。1962年に職業俳優と演劇人養成のために設立した付設「韓国演劇アカデミー」はその後「ソウル芸術専門学校」(1974年)を経て、1998年には「ソウル芸術大学」に発展した。
1962年春のドラマセンター開館に関連する記事は「東亜日報」と「京郷新聞」と「毎日経済新聞」だけで377件に上り、当時の韓国社会で大きな話題だったことがわかる。しかしドラマセンターはオープンしてまもなく財政難にみまわれ、その後「ソウル文化財団」が運営にあたり名称も「南山藝術センター」と変更されるなどさまざまな変化を経たが2020年12月31日付で閉館した。現在は南山芸術センターデジタルアーカイブとして残されている。
 設立当時の「ドラマセンター」外観
設立当時の「ドラマセンター」外観

【解説】韓国南部の統營(トンヨン)出身の児童文学者・朱萍(チュ・ピョン、1929〜)を代表として1962年に創団された児童劇団「セドゥル(鳥たち)」は、1963年から1965年にかけて3回にわたる日本公演を行った。韓国の新聞記事によると最初の日本公演は「日本亜細亜友之会」の招請で、居留民団と東京韓国学園などが後援となって実施された。上演作品は『森の花の精』(朱萍・作)や『うさぎ伝』(朱萍・作、李城・演出)などで、公演は北九州地方から始まり関西・関東を経て東北地方まで巡回した。朝鮮日報は「日本へ行く児童劇団セドゥル」(1963/6/22)という見出しの記事で、韓国の児童劇団「セドゥル」の最初の訪日公演を報道した。
日本公演を終えたチュ・ピョン代表は東亜日報(1963/10/19)紙上で日本の児童演劇の現況を紹介するとともに、セドゥルの舞台が日本で好評を得たこと、特に成人演技者ではなく児童が舞台に立って演じるというセドゥルのスタイルが珍しがられたと語った。
翌1964年は「日本児童演劇協会」の招請で日本公演を行った。当時の日本児童演劇協会会長であった栗原一登(1911〜94)が主導して招聘し、同協会の北島春信(1927〜)の引率によって、戦前から劇教育で有名な成城学園で児童たちに見せたという(日本児童演劇協会、2011年4月6日)。上演作品は前回と同じく『森の花の精』や『うさぎ伝』などで、これらの作品とともに韓国の歌や舞踊が演じられた。しかし1965年の第3回めの日本公演では、前回の公演で「物議をかもした日本の歌はうたわない」(京郷新聞、1965/11/3)ことにしたという。このことから当時の韓国社会ではたとえ児童劇団であっても日本の歌をうたうことはタブーであったことがわかる。
セドゥルの日本公演は1965年以後は行われなかったようで、60年代の日・韓間の児童演劇交流はこれ以上には活性化しなかった。しかし後述するように、セドゥルとの交流は日・韓間の人の往来が容易ではなかった時代に日本演劇人が韓国演劇に接する機会をもたらした。1965年に栗原と北島がチュ・ピョンの招請で韓国を訪問することになったのである。
東亜日報は1963年8月19日付けの記事「児童劇団セドゥル、渡日」で「セドゥル」の訪日公演を報道した。

東亜日報(1964/7/25)は「日本へ行く子供劇団/セドゥル、来月出発予定」で、「セドゥル」の3度めの訪日公演を報道した。

1964年10月に開催された東京オリンピック直後の同年11月、日本と韓国の共同制作作品を東京会館で上演した。韓国の元老演劇人である柳致眞(ユ・チヂン、1905〜74)の『自鳴鼓』を青山圭男(1903〜1976)が構成・演出し、作曲は夏田鍾甲(禹鍾甲、1916〜?)が担当した。主演にはこの当時日本で韓国舞踊を教えていた金順星(キム・スンソン)が務め、国際アーチストセンターの会員など多数の舞踊家が出演した。


劇作家の栗原一登(劇作家、当時は日本児童演劇協会会長)が北島春夫とともに韓国演劇協会の招請で5月末から6月中旬まで韓国を訪問した。そして韓国各地で児童劇や大学演劇を観覧し、ソウルの「ドラマセンター」などを訪問した。その時に見聞したことを朝日新聞1965年6月23日に「韓国の演劇を見て<上>」という記事を、そして翌6月24日に「韓国の演劇を見て<下>」という記事を寄稿した。



韓国の劇団「山河(サナ)」は福田恆存(1912〜94)の戯曲『解ってたまるか!』を『孤独な英雄』と翻訳・改題して国立劇場で上演した(〜4/13日)。翻訳は韓国の元老演劇人で日本語の堪能な車凡錫(チャ・ボンソク、1924〜2006)が行い、演出は「山河」の創団同人である表在淳(ピョ・ヂェスン、1937〜)が当たった。東亜日報の「日本知識人風刺劇、『孤独な英雄』公演/劇団山河」(1969/4/11)で簡略に紹介された。『孤独な英雄』の底本となった『解ってたまるか!』は1968年2月に起きた「金喜老事件」を素材にして、福田恆存が劇団四季のために書き下ろした作品である。